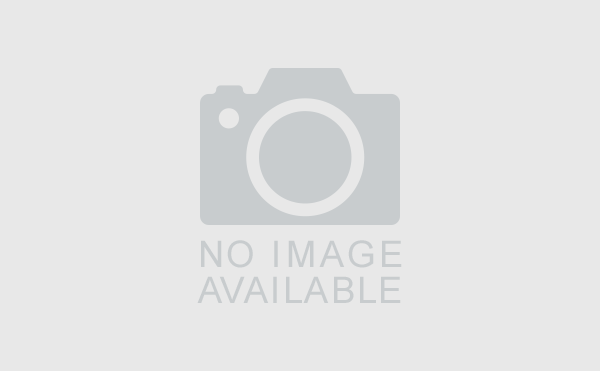相続人の中に行方不明者や認知症の方がいる場合手続きはどうなりますか?

行方不明者と認知症
【ご相談内容】
姉が20年以上音信不通です。おそらく健在だとは思いますが、どこに住んでいるのかも、連絡先も不明です。相続人は、被相続人の子である自分と姉、そして90歳になる母ですがこちらも認知症で施設に入所しています。亡くなった父名義の不動産の名義変更をしたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
【アンサー】
結論、行方不明者である姉については①不在者財産管理人を選任する②失踪宣告申立を行う の2択かと思います。認知症のお母さまに関しては、法律行為ができない重度の認知症の場合は①成年後見制度の利用が必要かと思われます。
遺産分割協議の相続人とは?
相続が発生し、遺言がない場合は原則遺産分割のためにまず協議を行うのが一般的です。
協議が調わない時やできない時は、遺産分割調停の申立を家庭裁判所に行うことも検討することになります。
遺産分割協議(遺産の分け方の話し合い)は、法定相続人全員で行う必要があり、行方不明の方や認知症の方を除いて協議を成立させることはできません。
行方不明者がいるとき
①行方不明の場合
不在者財産管理人(行方不明者の財産を管理する人)を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。
不在者財産管理人が遺産分割協議に参加する場合は権限外行為のため、家庭裁判所の許可も必要となります。
②7年以上生死不明の場合
生きているかもわからなく、7年以上経過している場合は失踪宣告を利用するケースもございます。
比較的稀なケースではございますが、認められれば通常の失踪の場合は生死不明になってから7年満了時に死亡したとみなされます。万が一、生きていて戻った場合は失踪宣告を取り消すことももちろん可能です。
認知症の方がいるとき
①成年後見人がおり、成年後見人自身も相続人の場合
→利益相反が発生しているため、後見監督人がいれば、後見監督人が代理で協議の参加します。後見監督人がいない場合は、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
②成年後見人がおり、成年後見人は相続人ではない場合
→後見人が被後見人を代理して遺産分割協議に参加します。
③成年後見人がいない場合
→遺産分割協議に参加する際に判断能力に問題がある場合は、成年後見人制度の利用が一般的です。
医師の診断書などを用意し、判断能力に問題ない程度の認知症や、歳相応の物忘れ程度の場合で法律行為の意味が理解できる場合は、遺産分割協議に参加することができます。
生前の対策はある?
人はいつか必ず亡くなります。
私自身も、25歳の頃はじめて自分自身の遺言書を作成致しましたので早すぎる、まだ若いからということは全くありません。
今回のようなケース(相続人に、行方不明者や認知症の方がいる)は近年とても増えており、相続が発生した場合は必ず相当の費用や手間、期間がかかります。
生前の対策1つで、防げることなので残していく家族のために必ず遺言書を作成しましょう。
当事務所は、遺言書の作成サポートには特に力を入れております。お気軽にご相談ください。